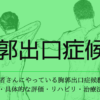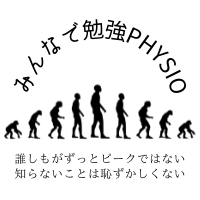上肢・肩・腕の痛み・痺れの原因で迷ったらこの検査で何の神経か調べよう!病院・リハビリでも使われるULTTを紹介します!
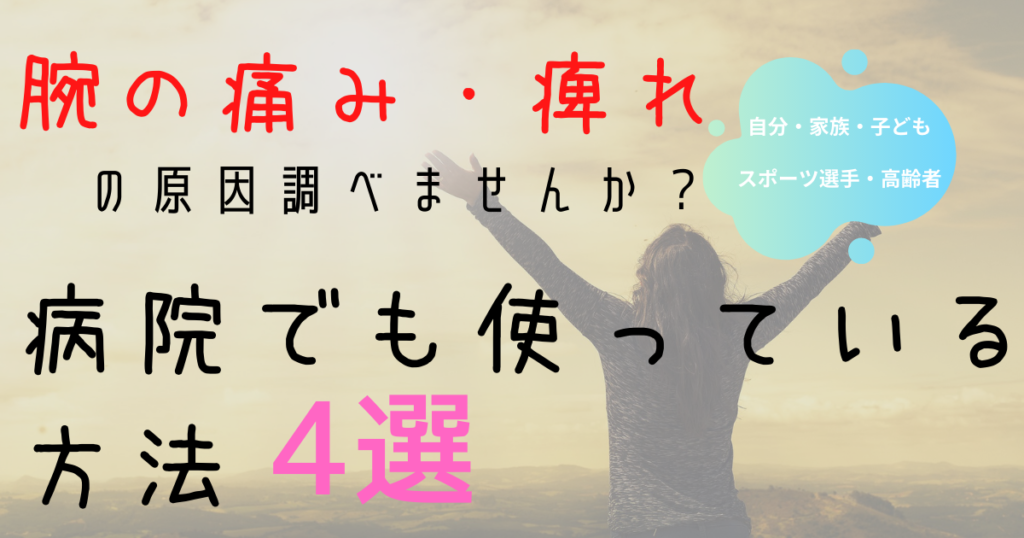
臨床で患者さんを診ていると、もしくは普段生活していると
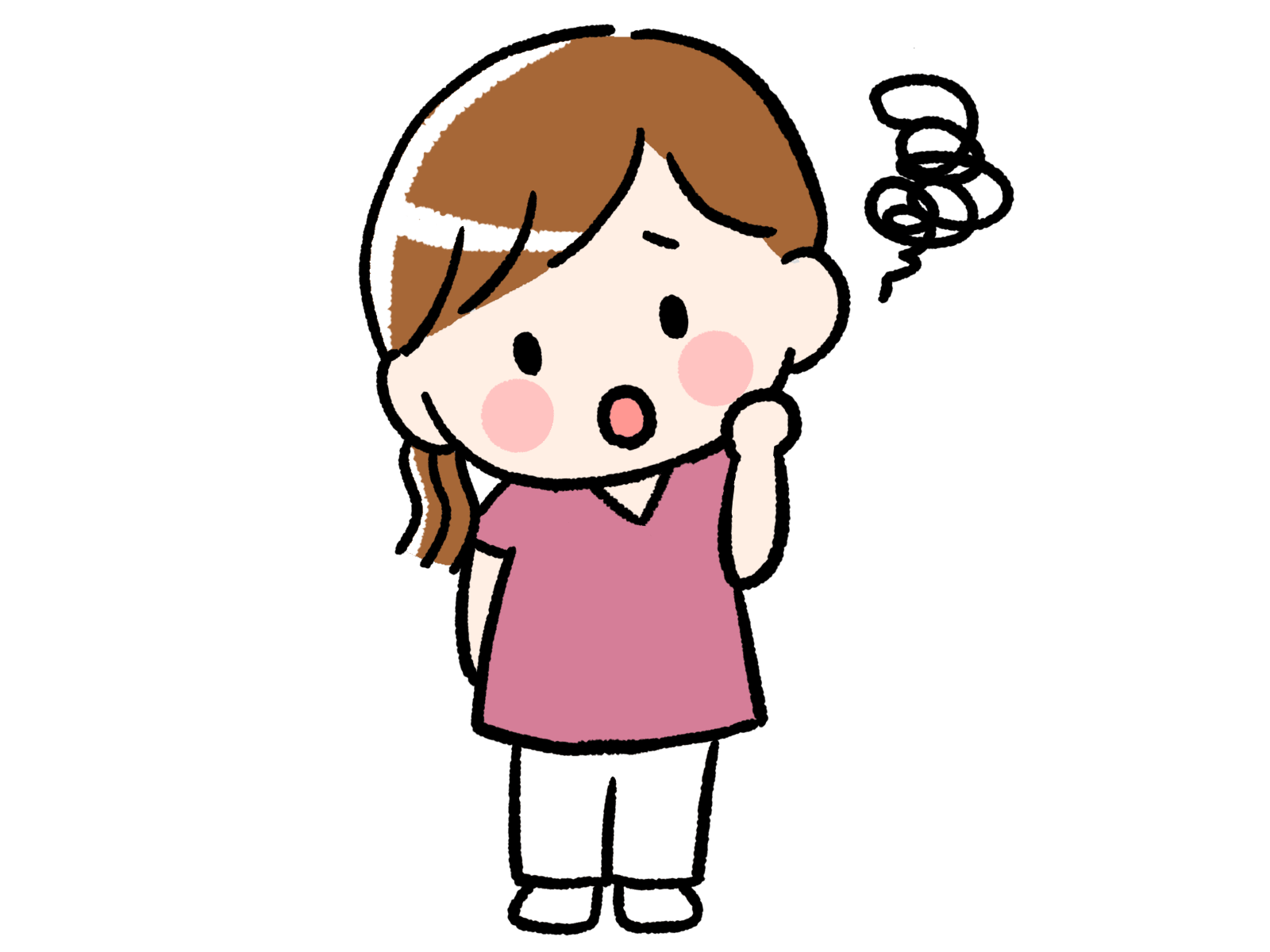
腕が痺れるんですけど・・・・
でも特に首のレントゲンで異常はないと言われました・・・

それは大変!じゃあまず評価しないとだね!
疼痛部位・アライメント・感覚・筋力・反射・・・・・・・
という場面は少なくないのではないかと思います。
そんな時、
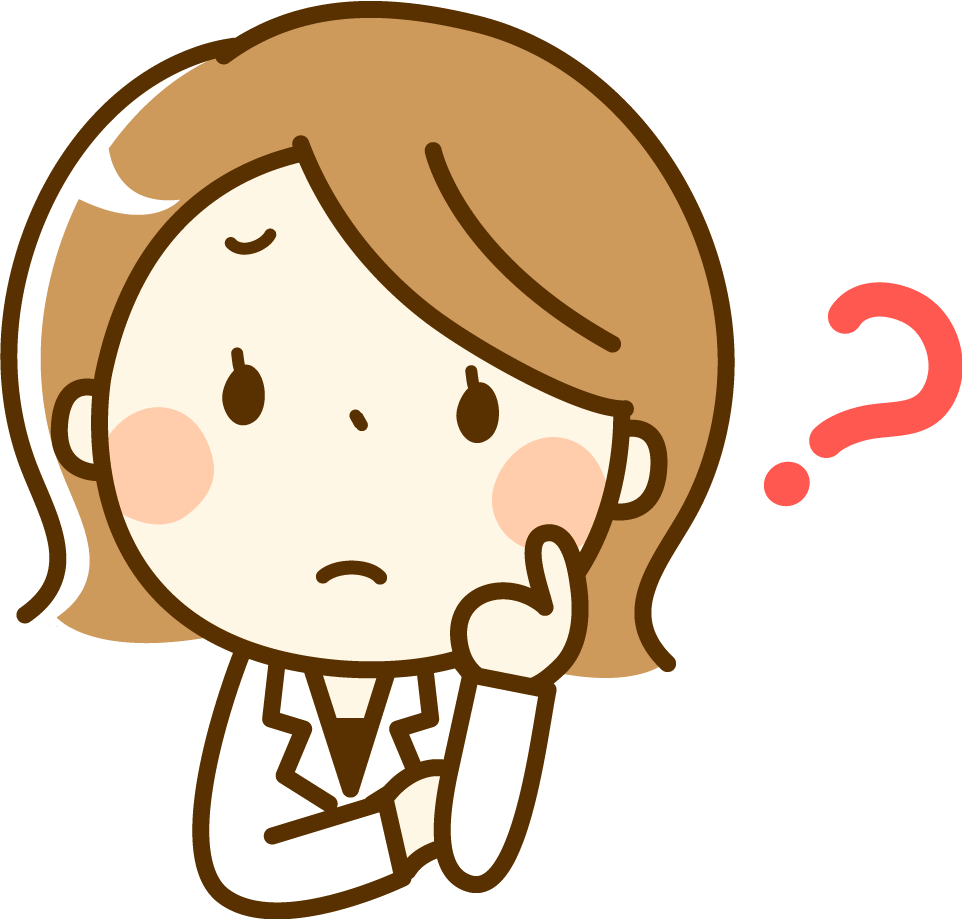
心の中
でも結局なんの神経が問題なんだ?腕神経叢のどれかの神経だとしても髄節レベルが被ってるのもあるし、どうやって神経を同定しようか・・・
と悩むこともあるのではないでしょうか。
一方で患者さんは
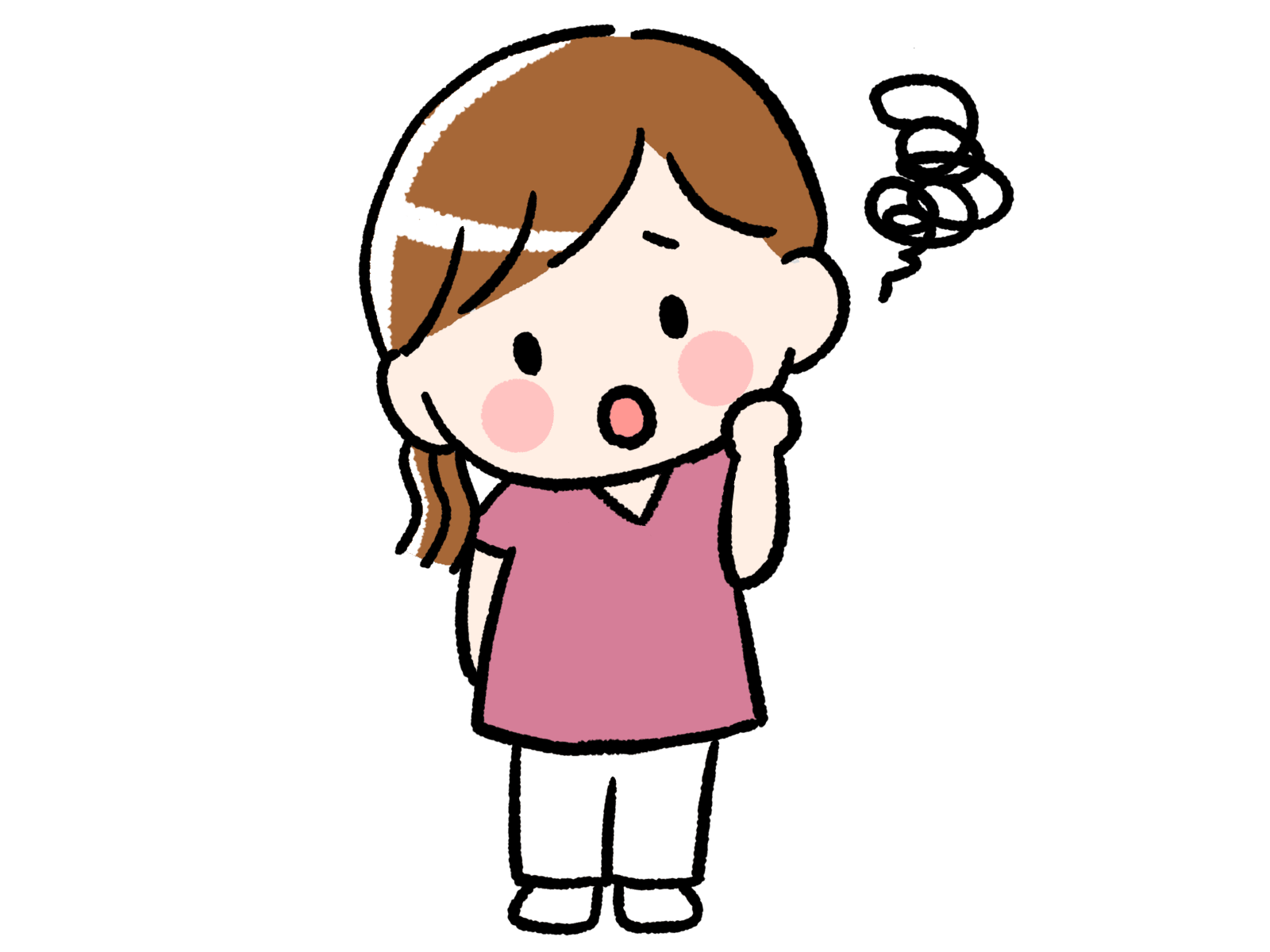
この痛みが本当に辛い・・・でも原因が分からない・・・
と、こんな感じになることも。。。
そんな時は
上肢緊張検査もしくは腕神経叢緊張検査(ULTT:Upper Limb Tension Test)を行うと神経が同定できるかもしれません。
頚椎症の方はストレートネックである可能性が多いです。肩こりは頚椎症の場合治していく必要もあるのですが、友人の理学療法士は親の肩こり解消のためにこれを購入していました!
上肢緊張検査・腕神経叢緊張検査(ULTT)
このテストは両腕に放散するような痛みや感覚低下・筋力低下などの末梢神経障害があるときに行われます。
例えば腕神経叢損傷・頸椎症性脊髄症・頸椎症性神経根症などと診断された場合や野球選手やバレーボール選手で腕をたくさん振っている人に検査することが多い印象があります。
検査の内容は、両腕に走っている神経をわざと伸ばして痛みを誘発させ、左右差を確認して異常かどうかを確認します。
別名「Elvey test」(エルビーテスト)とも言われるようですが、この名前は実際にはあまり聞いたことないですね・・・・
腕神経叢とは
腕神経叢とは、頭から背骨の中を通っている神経から枝分かれし、肩・腕・手・指へと向かう神経の総称のことです。そのため、腕神経叢と言っても色々な神経があるわけです。
例えば
・正中神経
・筋皮神経
・腋窩神経
・尺骨神経
・橈骨神経
などの5つの神経ですね。
これらの神経は当然のことながら、背骨の中を走っている神経から枝分かれしたあとに指の方に向かうのですが、その走行は全て異なります。
よって、腕の動かし方によって伸ばされる神経が変わってくるので、その性質を使おうというわけです。
この検査は4つの方法に分けられます。それぞれでどこの神経が伸ばされるのかが違いますのでしっかり覚えましょう。
では実際にどう行うのかを説明して行きます。
ULTT 1(正中神経)
肩甲骨下制→肩関節外転110°→肩関節外旋→前腕回外→手関節伸展→手指伸展→肘関節伸展!!
最後の肘関節伸展(肘を伸ばす動き)で疼痛・痺れが出現します!
細かくは正中神経と前骨間神経が伸張されます。
詳細の方法・内容はこちら
ULTT 2 Med もしくはULTT 2a (正中神経)
肩甲骨下制→肩関節外旋→肘関節伸展→前腕回外→手関節伸展→手指伸展→肩関節外転!!!
最後の肩関節外転で疼痛・痺れが出現します!
このテストでは正中神経が伸張されます。
詳細の方法・内容はこちら
ULTT 2 Rad もしくはULTT 2b(橈骨神経)
肩甲骨下制→肩関節内旋→肘関節伸展→前腕回内→手関節屈曲→手指屈曲→肩関節外転!!!
最後の肩関節外転で疼痛・痺れが出現します!
このテストでは橈骨神経が伸張されます。
詳細の方法・内容はこちら。
ULTT 3(尺骨神経)
肩甲骨下制→肩関節外旋→肘関節屈曲→前腕回内→手関節伸展→手指伸展→肩関節外転!!!
最後の肩関節外転で疼痛・痺れが出現します!
このテストでは尺骨神経が伸張されます。
詳細の方法・内容はこちら。
みるべきポイント
試しにやってみるとわかると思いますが、これは健常な人でも痛みが生じます。
重要なのは、「左右差」です。
左右ともに同じくらいの強さ・範囲で動かしているのにも関わらず、どちらか一方の腕の痛みが強く出現する場合に「陽性」と判断できます。
検査をやってはいけない時・禁忌
このテストは神経を引き伸ばすテストです。
そのため、この神経が悪化している時や、大元の背骨の神経が傷んでいる時に「おりゃー!」と神経を引っ張ったらさらに悪くなりそうですよね?
よって
・神経症状(痺れや痛み)がどんどん悪くなっていっている時
・神経症状が非常に強く、夜間痛などが出現するほどの急性期にある時
・背骨を走っている神経(脊髄神経)に病気がある時
などです。
治療・リハビリ
さて、これらのテストが陽性だった場合、どうするのか・・・?ですよね。。
これらによって神経が同定・予測できたとしても、
「どこで・なぜ・どうしてこの神経が障害されているのか」
をさらに考える必要があります。それには
・神経の走行を確認する
・神経がどの筋肉を貫いているのか、どの筋肉の間を走っているのか
を見てみると何か見えてくるかもしれません。
すると、
・中斜角筋のリラクゼーション
・小胸筋のリラクゼーション
・肩甲帯固定筋の筋力トレーニング
・胸椎伸展可動性向上や姿勢修正
などを行ったほうがいいのでは・・・・・・?
と考えられるかもしれません。あくまでも一例ですが・・・
または神経モビライゼーションという手もあります。身体の中で神経が上手く滑走しないとスムーズに動かないため、神経が障害されるという場合に適応になります。
方法はそれぞれで異なりますので、各テストの詳細説明を見てください。
⇨ ULTT1・ULTT2 Med (2a)・ULTT 2 Rad (2b)・ULTT3
リハビリテーション専門職の方であれば当然画像の読影が必要になってきます。
しっかりと勉強して画像からもヒントを得られると相当有利になると思います😁
胸郭出口症候群についてのまとめはこちら!その痺れ・痛みは胸郭出口症候群が原因かも!?
まとめ
今回は腕などに痺れや痛みが生じた時に、何の神経かを同定するためのテストである「上肢緊張検査・腕神経叢緊張検査(ULTT)」を紹介しました。
少しでも今後の臨床や医療機関への受診のきっかけになれば幸いです。
一般の方も痛みの不安や心配になることがあれば医療機関への受診をお勧めします。
あくまでも個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではありません。実際に行う場合は各自の判断と責任で行うようお願い致します。また当記事の目的は、医療従事者以外の方が各々で判断できるようにすることではありません。納得して医療機関にスムーズに受診が出来るようなアドバイス、もしくは新人の医療従事者向けとなりますので、無理な範囲を超えて行わないようお願い致します。
Butler,D.S.: Mobilisation of the Nervous System. Melbourne, Churchill Livingstone, 1991

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/218dfc9d.bafe89a7.218dfc9e.637ea020/?me_id=1384574&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftechlove%2Fcabinet%2F08181767%2F08181769%2Fimgrc0088063085.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
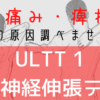
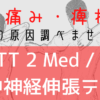
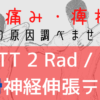
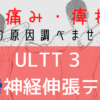
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acd1cf2.2c88150f.1acd1cf3.fed0e12e/?me_id=1278256&item_id=16503821&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8354%2F2000005238354.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)